北陸新幹線延伸は失敗だったのか?敦賀止まりの光と影
本ブログサイトでは、2024年3月に北陸新幹線が敦賀まで延伸開業して以降、一度北陸新幹線の延伸をテーマに記事を投稿しました。
敦賀まで新幹線が開業したことを有意義なものとみなしながらも、同時に批判的な立場で延伸開業を評価しています。
これは、私が2024年3月の北陸新幹線開業を、素直に高く評価できないと考えているからであります。
敦賀延伸から1年。開業後の出来事と共に、「敦賀まで」延伸したことへの個人的な意見を述べていこうと思います。
前回の記事
新幹線が延伸したのに、時短メリットがほとんど無い
一般的に新幹線が開業して期待されることに、時間短縮効果があります。
1964年の東海道新幹線開業にしろ、東北新幹線開業にしろ、北陸新幹線金沢延伸(2015年)にしろ、新幹線の開業を通じて、従来の鉄道ルートよりもはるかに短い時間で移動できるようになりました。在来線特急よりも新幹線の速度が速いので、これは当然のことです。
しかし、2024年3月の北陸新幹線敦賀延伸では、目に見える時間短縮は実現しませんでした。単純に考えれば、北陸ー関西間で大幅な時間短縮を見込めますが、それは起こらなかったのです。
開業前と開業後の比較で、どれだけ所要時間に変化があったのかを見ていきましょう。
①金沢ー大阪間
2024年3月16日以前、特急サンダーバードは次のような所要時間で、金沢ー大阪間を走破していました。(2023年度の定期列車を参考)
| 特急名 | 所要時間 |
| サンダーバード2号 | 2時間45分 |
| サンダーバード8号 | 2時間48分 |
| サンダーバード40号 | 2時間38分 |
これは全て上り列車ですが、基本的にこれくらいの時間で同区間を走破していました。ちなみに「サンダーバード40号」は、途中停車駅が福井、京都、新大阪だけのサンダーバード最速列車で、すなわち2時間38分が金沢ー大阪間の最短所要時間でした。

続いて、2024年3月16日以降、敦賀で新幹線と特急サンダーバード号の乗り換えを要する場合の移動時間を見ていきましょう。
(表の移動パターンは、全て金沢から大阪へと移動する場合を想定しています。2024年度の定期列車を参考)
| 北陸新幹線の列車名 | サンダーバード号の列車名 | 敦賀駅での乗り換え時間 | 移動だけの所要時間 | 乗り換えを含めた所要時間 |
| つるぎ31号 | サンダーバード32号 | 8分 | 2時間8分 | 2時間16分 |
| つるぎ33号 | サンダーバード34号 | 12分 | 2時間22分 | 2時間34分 |
「つるぎ31号+サンダーバード32号」にあるように、敦賀駅での乗り換え時間は最短で8分となっていて、おそらくこれがJR西日本の考えうる、「誰もが無理なく移動できる乗り換え時間」ということでしょう。
しかもこの2列車は、共に停車駅が最も少ないため、おそらく2024年3月以降の金沢ー大阪間の最短所要時間は、2時間16分であります。
特急サンダーバード時代は2時間38分が最短時間であったため、12分の短縮と言えます。
②福井ー大阪間
2024年3月16日以前、特急サンダーバードは次のような所要時間で、福井ー大阪間を走破していました。(2023年度の定期列車を参考)
| 特急名 | 所要時間 |
| サンダーバード2号 | 2時間 |
| サンダーバード8号 | 2時間 |
| サンダーバード40号 | 1時間54分 |
停車駅の数に問わず、基本的には2時間ほどで福井から大阪まで移動できました。先ほどと同じように「サンダーバード40号」は同区間の最速列車で、途中の停車駅は京都と新大阪だけです。

続いて、2024年3月16日以降、敦賀で新幹線と特急サンダーバード号の乗り換えを要する場合の移動時間を見ていきましょう。
(表の移動パターンは、全て福井から大阪へと移動する場合を想定しています。2024年度の定期列車を参考)
| 北陸新幹線の列車名 | サンダーバード号の列車名 | 敦賀駅での乗り換え時間 | 移動だけの所要時間 | 乗り換えを含めた所要時間 |
| つるぎ31号 | サンダーバード32号 | 8分 | 1時間43分 | 1時間51分 |
| つるぎ33号 | サンダーバード34号 | 12分 | 1時間46分 | 1時間58分 |
この2パターンは、先ほどの「金沢ー大阪間」で紹介したもので、停車駅の数に違いがあります。
「つるぎ31号+サンダーバード32号」が、福井ー大阪間の最短時間でしょうが、なんとその時間は移動込みで1時間51分。特急サンダーバード時代と3分しか差が無いのです。
時短効果がほとんど無いが、特急料金は値上がり
このように、金沢ー大阪間、福井ー大阪間ではほとんど時間短縮が実現しなかったにも関わらず、特急料金は、特急サンダーバード時代と比較して、実質値上がりしました。
新幹線は在来線特急と比較すると、特急料金は高いので当然なんですが、時間短縮の割には…という不満は確かにあるでしょう。
①金沢ー大阪間(特急料金は通常期)
| 特急サンダーバード時代(2023年度) | 北陸新幹線+特急サンダーバード(2024年度) |
| 運賃:4,840円 特急料金:2,950円 | 運賃:4,840円 特急料金:4,570円 |
| 合計:7,790円 | 合計:9,410円 |

②福井ー大阪間(特急料金は通常期)
| 特急サンダーバード時代(2023年度) | 北陸新幹線+特急サンダーバード(2024年度) |
| 運賃:3,410円 特急料金:2,730円 | 運賃:3,410円 特急料金:3,880円 |
| 合計:6,140円 | 合計:7,290円 |

駅によっては料金差に違いがありますが、金沢、福井から大阪に行く場合は、新幹線開業後に特急料金が実質値上がりしました。
しかし先述のように、今回の開業で同区間の時間短縮はほとんどありませんでした。その上、敦賀での乗り換えが必要です。
敦賀駅での乗り換え動線には、最大限の工夫がされており、大量の乗客がスムーズに乗り換えできるように設計されてはいますが、そうは言ってもこの値上がりを受け入れられるか、人によって意見が分かれると思います。
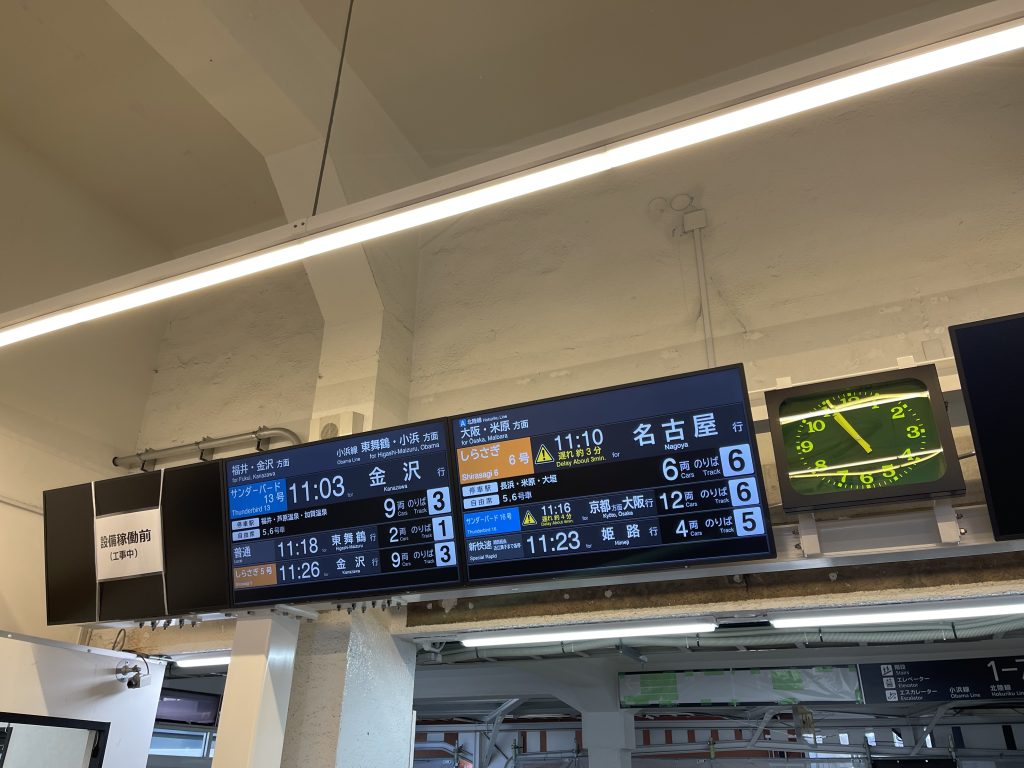
「東海道新幹線のバイパスになる」という意見
しかし、北陸新幹線敦賀延伸は必ずしも、悪いことばかりではありません。特に2024年は、敦賀まで伸びた北陸新幹線が活躍した1年でもありました。東海道新幹線の迂回ルートとして役目を果たしたのです。
2024年中に幾度か、東海道新幹線は大規模な運休に見舞われました。台風や大雪といった自然災害によるものもありましたし、設備トラブルによる運休もありました。
特に自然災害の面では、北陸新幹線は東海道新幹線と対照的な強さを誇ります。両路線ともに沿線に豪雪地帯を抱えていますが、降雪時の定時運行という点では、北陸新幹線の右に出る者がいないでしょう。北陸に雪が降ろうが運休になりにくいですね。
一方で東海道新幹線は、関ヶ原の雪で従来から遅れやすく、太平洋側の台風の影響も受けやすいため、運休の発生が数多くあります。
https://news.ntv.co.jp/category/society/a2a9a84902214db3a9cf226728268341
2024年8月には設備トラブルもありました。
https://jr-central.co.jp/news/release/_pdf/000043732.pdf
このような運休があった中で、北陸新幹線は大動脈の補完として役目を果たしました。
もちろん、あれだけの本数と乗客数がある東海道の移動客全員をカバーすることはできませんが、それでも迂回ルートがあるに越したことはありません。実際、「東海道新幹線の運休」が発表されると、サンダーバードと北陸新幹線のシートマップは即座に埋まり、臨時列車を運行させる、という事例も数多く見られました。
このような出来事を踏まえて、敦賀まで延伸した北陸新幹線を評価する意見も見られるようになりました。
「敦賀という中途半端な延伸に不満や欠点はあるが、東海道のバイパスルートとして機能しうる」という論調で利点を見出す意見もあったと思います。
このような意見を見ると、北陸新幹線が敦賀まで延伸したからバイパスになった、と思ってしまいますが、私はそう思いません。
「北陸新幹線が東海道のバイパスになった」のは、2024年3月ではなく2015年3月、つまり金沢延伸時にすでにそうなっていたと考えています。

すでに金沢延伸で東海道のバイパスになった
現在、東京ー大阪間を北陸新幹線と特急サンダーバードを乗り継いで移動すると、5時間程度かかります。
東海道新幹線のぞみ号の2倍に当たる所要時間です。
では北陸新幹線が金沢止まりだった時に、新幹線+特急サンダーバードで移動するとどれくらいかかったのか?という話です。
結論を申し上げると、それほど変わりません。いつか乗り継ぎパターンをご紹介します。
以下の表は、東京から大阪へと移動する際の乗り継ぎパターンです。(2023年の定期列車ダイヤを参考)
| 北陸新幹線の列車名 | サンダーバード号の列車名 | 金沢駅での乗り換え時間 | 移動だけの所要時間 | 乗り換えを含めた所要時間 |
| かがやき501号 | サンダーバード14号 | 19分 | 5時間2分 | 5時間21分 |
| はくたか559号 | サンダーバード26号 | 18分 | 5時間47分 | 6時間5分 |
はくたか号に乗車するパターンは、はくたか号の停車駅の関係上、所要時間は伸びていますが、どっちにしろ敦賀延伸後の乗り継ぎと比較すると、1時間程度の所要時間差に収まっています。
このことから分かるのは、東海道のバイパスルートになったのは、敦賀まで延伸した時ではなく、金沢まで延伸した時だったということです。
1日を通して東京ー大阪間を5時間で移動可能になったのは敦賀延伸時ですが、それでも金沢延伸時からバイパスルートとして機能できる所要時間だったのだと思います。

バイパスルートということは、既に事例があるように、一度に多くの乗客が北陸新幹線に流れ込んできます。そのような点では、金沢駅よりも、最初から「大量の乗客による乗り換え」を想定して設計された敦賀駅で乗り換えする方がスムーズではあるかもしれません。
しかし、バイパスルートの確立が敦賀延伸によるものか、と問われると、半分正解だし半分不正解、ということが私の意見です。
まとめ
北陸新幹線の乗客数推移は、概ね好調です。
開業パワーによるものなのかどうかは、今後の行く末次第ですが、どっちにしろ大阪までの開業の目処をつけない限りは、完全なるバイパスルートとは言えないでしょうし、暫定的なものであるはずの「敦賀乗り換え」が長期化し、少なく無い不便を生み出してしまいます。
JR各社と沿線自治体の協議で、一刻も早く延伸の決着がつくことを願っています。
